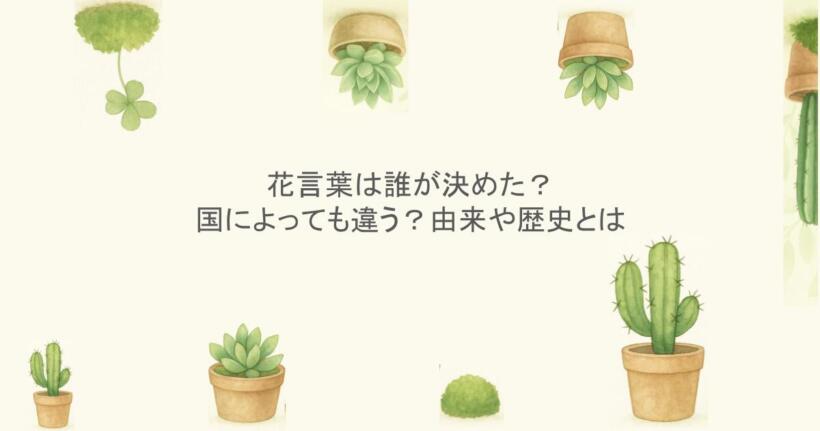花言葉は誰もが一度は耳にしたことがある花に込められた特別な意味ですが、一体だれが決めたのか、国によってちがうのか疑問に思ったことはありませんか?この記事では、花言葉の起源や歴史、国ごとに変わる面白い違いをわかりやすく解説します。知ればもっと花を贈るのが楽しくなる、会話のネタにもなる花言葉の世界へ一緒に踏み込んでみましょう。
目次
花言葉は誰が決めたのか?
花言葉は「誰が決めたのか?」と聞かれると実は明確な答えはなく、1人の天才がパッと作り上げたわけでも、どこかの公式機関が決めたわけでもないのです。実際には、長い歴史の中でさまざまな文化や文学、宗教的背景が複雑に絡み合いながら少しずつ作られてきました。
19世紀のヨーロッパで流行した「フラワー・ランゲージ(花言葉)」は恋愛や感情を秘密裏に伝える手段として発展し、その影響は世界中に広がっています。このように花言葉は1人の力で決められるものではなく、文化が生み出した”言葉なきメッセージ”の集まりなのです。
花言葉のルーツはヨーロッパ
19世紀のヨーロッパで誕生した「フラワー・ランゲージ」は、花を使って言葉を交わす秘密のメッセージとして大流行しました。特にヴィクトリア朝時代のイギリスでは、直接言葉にしづらい感情や愛の告白を花に託して伝える文化が社交界を中心に広がったのです。
例えば赤いバラは熱烈な愛情、スミレは謙虚さを象徴し、その言葉の意味を知る人同士で花を送り合うことで”ささやかな会話”が成立しました。この花言葉文化は詩人や作家たちの手によってさらに豊かに彩られ、今日に伝わるロマンチックなイメージを形作っています。
日本に花言葉が伝わったのは明治時代
日本に花言葉が伝わったのは明治時代のことで、西洋文化が次々と流入する中で欧米から花言葉の考え方も日本に紹介されました。当時の日本は海外の園芸書や文学を通じて花に意味を込める風習を知り、日本の伝統文化と融合させていったのです。
和歌や俳句では古くから花や季節に特別な意味が込められていましたが、西洋のロマンチックな花言葉が加わったことで「和洋折衷」の独自スタイルが生まれました。現代の花言葉に感じる繊細さや奥深さは、まさにこの歴史的な背景から来ていると言えますね。
国ごとに違う花言葉①菊
国ごとに違う花言葉をいくつか紹介すると、菊は日本と海外ではまったく異なる花言葉を持つ花。日本では「高貴」「長寿の象徴」として敬われ、天皇家の紋章に使われるほど特別な花ですが、ヨーロッパでは「死」「悲しみ」といったイメージが根付いています。
アメリカでは明るくポジティブなイメージが強く「友情」「幸福」「元気」といった花言葉があり、秋の季節を祝う花束にもよく登場します。中国や韓国でも「長寿」「繁栄」などお祝いの場で親しまれる花で、文化の違いが生む花言葉のギャップはときに驚きと学びを与えてくれますね。
国ごとに違う花言葉②バラ
バラは世界中で愛されながらも、花言葉は国によって微妙に意味が変わる面白さがあります。日本で赤いバラは「告白」「愛情」、ピンクは「感銘」、白は「清純」など色ごとに違い、中国でも赤は「真実の愛」、黄色は「祝福」として使われます。
フランスで赤は「愛の宣告」と強い情感が込められ、黄色は「嫉妬」「裏切り」といった少しネガティブな意味も。韓国でも色によって異なり、青いバラは「不可能」「奇跡」を表す花言葉が新たに加わりました。こうした色や国による違いを知ると、花を贈るときにより奥深さを実感することができます。
国ごとに違う花言葉③チューリップ
チューリップの花言葉も少しずつ意味が異なり、もともとトルコ原産のチューリップは神聖な花として「神の祝福」「完璧な愛」として大切にされてきました。オランダに伝わってからは伝説にちなんだ「博愛」「真面目な愛」が花言葉として浸透、春の訪れを告げる象徴となっています。
日本では全体的に「愛の告白」「思いやり」とポジティブな意味が中心ですが、赤は「真実の愛」、白は「新しい愛」、黄色は「望みのない恋」など違いがあります。花言葉の奥深さを知って、贈る相手やシーンなどにぴったりのチューリップを選んでくださいね。
花言葉が違う理由
花言葉が国や地域ごとに違うのは、歴史や文化・宗教・気候といったさまざまな要素が深く関係しているから。日本では四季の移ろいや和歌・俳句の文化的背景が花言葉に繊細な意味をもたらしました。ヨーロッパではキリスト教の象徴や神話が花に意味を与え、全く別のイメージが定着しています。
花の色や形、その効用に関する認識も国ごとに異なり、同じ花でも言い伝えや解釈が変化してきたのです。さらに新しい品種が生み出されるたびに、その開発者や地域で独自の花言葉がつけられることもあり、花言葉は時代とともに変化し続けています。
日本独自の花言葉の面白さ
日本独自の花言葉は、明治時代に西洋より花言葉の文化が入ってきてから、日本人の美意識や季節感、歴史・風習に合わせて独自に発展しました。日本では特に文化と深く結びつき、花の持つ繊細な表情や季節の移ろいに意味を込める傾向があります。
例えば桜は「儚さ」「精神美」、梅は「忍耐」「希望」を象徴、単なる花言葉以上に日本人の心情や自然観が反映されています。このような背景から、日本の花言葉はとても繊細で感情豊かな表現が多く、贈り物やコミュニケーションのツールとして日常生活に溶け込んでいるのです。
花言葉を知ると贈り物がもっと楽しくなる
花言葉を知ると贈り物がもっと特別なものになり、プレゼントに花言葉を添えることでただの花束が「気持ちを丁寧に伝えるメッセージ」へと変わるのです。贈る相手やシーンに合わせて花言葉を選べば、気持ちがより深く伝わりやすくなります。
本数にも意味があったり、同じ花でも明るい花言葉・怖い花言葉があったり、そこにはさまざまな意味・理由があります。花言葉の記事で種類や色別の意味まで詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
まとめ
花言葉は誰が決めたか気になっていた方も多い方ともいますが、文化や歴史、人々の想いが織りなす”生きた言語”のようなものだとわかりました。国や時代によって意味は異なってそれが花言葉の面白さでもあり、由来や意味を知っていると花束もより特別なメッセージに変わります。愛や感謝、励ましといった気持ちを花束に込めて伝えることで、贈る側も受け取る側も心が豊かになるはずです。